

パパスの特集③
極太ゴシックなおじいさん
塚野丞次の
フーテン人生と
荒牧太郎の天才伝説!
撮影・インタビュー/山下英介
パパスをつくった荒牧太郎さんはもういないけれど、このブランドを語るうえでは欠かせないキーパーソンが、もうひとりいる。パパスの創設以来、そのカタログや広告の制作を一手に手掛けてきた株式会社ビービーの代表、塚野丞次さんだ。塚野さんはなんと1936年生まれ! 一度見たら忘れられない手描きのロゴも、広告でよく見かける極太ゴシック文字を駆使したビジュアルも、彼がつくりあげたものだったんだ。なんでも彼は、単なるアートディレクターの枠を超えて、パパスというブランドの成り立ちに深く関わってきたのだという。これはぜひお話を伺っておかねば!と現在は鎌倉近辺に居を構える塚野さんのもとに伺ったのだが、ここでぼくたちは衝撃的な光景を目にすることになる。こんなにすごいご自宅も、こんなに渋くて軽やかで面白いおじいさんも、今まで見たことないぞ! パパスというブランドがますます魅力的に見えてくるインタビューを、じっくりと読んでみて。
このおじいさんは何者なんだ?
〝能舞台もどきのある家〟に
住む夫婦






屋外のトイレやお風呂はもちろん飾りじゃない! 塚野さんによると、開放的で気分がいいらしい。



キッチンもご覧のとおり。鉄製品は潮風の影響で、数年で錆だらけになるそう。

・・・えー、今日塚野さんにはパパスのことをたっぷり伺おうと思ったんですが、ご自宅のあまりのすごさに言葉を失っております。まるで鎌倉武士のお屋敷ですね。いきなり脱線しちゃって申し訳ないのですが、まずはこのご自宅について伺わずにはいられないのですが(笑)。

塚野 ここはぼくの実家だったんですよ。生まれたのは新潟県なんですけど。60 年くらい六本木に住んでいたんですが、ここがなかなか売れないのでもう住んじゃおうということで、ちょっと前に引っ越してきたんです。母が亡くなって以来、10年以上誰も住んでいなかったので、ほとんど廃屋でした。基本的にはもとの図面通りなんですが、芸大の人たちを巻き込んで2年かけてリノベーションしたら、こんなことになっちゃったんです(笑)。
こんなことになっちゃったんですか(笑)。この屋根しかない居間はなんて呼べばいいんですかね?

塚野さんの奥様 板の間って言ってますけど。私が能を習っているので、建築家が面白がって〝能舞台のある家〟ということで。
塚野 冬は薪をくべれば暖かいんですが、夏はほとんど使えない。まあ居間もトイレもここだけじゃないからね(笑)。でも台風が来た時なんかは風が抜けるから助かるよね。
奥様 台風の後は、床にできた水たまりがきれいですよ。鏡みたいでしばし見惚れる感じ。なんでも風情と思わないとね(笑)。
もう絶句です(笑)。奥様が着ていらっしゃる芭蕉布の着物にも衝撃を受けましたが、家具や調度品も素晴らしいですね。

塚野 いや、家具はほとんど六本木に住んでいるときに買ったものなんですよ。嫁さんがそういうの好きだから。
奥様 ここのために買ったものなんてソファーくらいだよね。それがなぜか、この家に合わせてあつらえたようになっちゃった。コレクションというわけではなくて、年とともに増えちゃった感じなんですが。ふたりでこんなにたくさん土鍋があってもしょうがないけど、捨てられないしね。

立木義浩さんに
食わせてもらった
六本木のフーテン時代
塚野 今日はこんなことが本題ですか(笑)?
す、すみません! それではそろそろ本題に入らせていただきます。塚野さんは鎌倉の実家から、いつ東京に来られたんですか?
奥様 そこから話し出すと、もう何日あっても終わらないわよ(笑)。
塚野 高校を卒業してからです。忌まわしい過去だから話したくないんだけど、東京ではフーテン暮らしをしていて。

奥様 忌まわしいって、文字にするとすごいね(笑)。
塚野 「きーよ」というジャズ喫茶に入り浸っていたんですけど、そこでフォトグラファーの立木義浩さんに出会って、しばらく食わせてもらっていたんです。歳は彼のほうがひとつ年下なんですけどね。
立木義浩さんや菊池武夫さんが入り浸っていた「きーよ」ですね。立木さんが仲間たちを養っていたという噂は、少し聞いたことがあります(笑)。
塚野 彼は二十歳くらいから稼ぎまくっていたから、くっついていると飯は食わせてくれるわ、ときどきお金は貸してくれるわで。あの頃はそういう連中がたくさんいたんですが、なかでもぼくが一番べったりでしたね。
その関係からデザイナーさんになるんですね。
塚野 これは仲間内じゃ有名な話なんですが、ぼくは立木さんのサインを使って、いつも勝手に中華料理屋で飯を食ってたんですよ。で、彼がひと月丸々ヨーロッパに行っていた間の請求書が届いたもんで、ついに気付かれて(笑)。こいつは遊ばしといちゃダメだということで、デザイン事務所に送り込まれたんです。

ひどい話ですね(笑)。
塚野 立木さんが怖かったから2年くらいいたけれど、遊びたい盛りじゃないですか。だから毎日朝方までジャズ喫茶で遊んで、眠い目をこすりながら事務所へ通うわけです。そんなの続くわけないですよね。ズル休みし続けて、しまいには行かなくなっちゃった。それでしばらくデザイン稼業はやめたんです。
立木さんの怖さよりも怠惰のほうが勝っちゃったんですね(笑)。なるほど、そこから奮起してビービーを立ち上げると。
奥様 ビービーにたどり着くまであと3日くらいかかるわよ(笑)。波瀾万丈なんだから。
塚野 ぼくの話は相当面白いんですよ(笑)。50〜60年代の〝六本木租界〟と言われていた時代の六本木のことなんか、たぶんぼくしか知らないんじゃないかなあ。ぜんぶ話すからぜひ本にしてください。
今日はパパスのプレスの方々もいらっしゃるので、ぜひ次の機会に(笑)。
イケイケのアートディレクター
がパパスを手掛けるまで

塚野 ずっと定職がなかったんですが、30歳のときにコスモPRという代理店に潜り込んだんですよ。社長のコネだったから、女性社員たちに白い目で見られたんですが、その後コスモアドという会社ができたので、そっちに移りました。コスモコミュニケーションズの前身ですね。
最近博報堂グラビティに社名変更した、あのコスモかあ。でも30歳っていったら、50年前の感覚でいえば立派な中年ですよね。
塚野 そうなの。だから遊んでいた連中がみんな落ち着いちゃって、ぼくなんかが会いに行くと煙たがられるわけです。それで仕方なくぼくも就職したんですよ(笑)。で、そのコスモでVAN JACKETやラングラーといったメンズファッションの仕事をやったんです。
それは続いたんですか(笑)?
塚野 遊んでばかりいたんですが、ラングラーで賞をいっぱいもらったんで、みんなに驚かれましたよ。お前みたいな奴がどうしてって。それで10年くらい働いたあとで、コスモを裏切って(笑)独立したんです。ラングラーの仕事をもってね。それが42、3歳の頃かな。

裏切りとはすごい表現。しかしまだ1970年代かあ(笑)。ついに満を辞してビービーの登場ですね!?
塚野 いやいや、それはフォードって会社だったんですよ。こんなの本当に何日もかかりますよ(笑)。
す、すみません。
塚野 フォードはいっしょにコスモを独立した岡って男とつくったんですが、そこがラングラーのハウスプロダクションみたいになって、ほかの仕事ができなくなっちゃったんです。それが面白くないので、ライフって会社をつくるんです。そしたら、そのライフも大きな会社になっちゃって。
フォードの次はライフですか。まだ現在の魯山人ばりのライフスタイルを送る塚野さんと全く結びつきません(笑)! しかしフーテンだったのに、やることなすこと上手くいっちゃうんですね。才能というべきか・・・やっぱり遊んでいたのがよかったのかなあ。
塚野 ラングラーの広告で賞をもらったから、業界的には知名度があったんですよね。いろいろ声がかかるもんで、どんどん大きくなっちゃったんですけど。それでそのあと、またアボットって会社をね・・・立ち上げたんですよ。
またですか! いったいいつになったらビービーの話が出てくるんですか(笑)?
奥様 ね、大変でしょ(笑)?


塚野 それで、フォードもライフもアボットもみんな稼いでいたから、あたしは何もしないでこれらのアガリだけで食べていこうと思って、塚野事務所をつくったんです。お前ら、俺にお金をよこすんだぞって(笑)。ところがどんどん不景気になって、アガリは勘弁してくださいって会社がではじめた。それで、「金くれないなら自分でやるよ」ってことで、アボットがやっていたパパスの仕事を塚野事務所に移して、ビービーという社名に変えたんです。1980年代後半だったかな。

おお、ついにパパスとビービーにたどり着きましたが、なんて不純な経緯なんだ(笑)。ちなみにビービーという社名にはどんな意味があったんですか?
塚野 ビービーは、もともとパパスの前身だった、ビービーケーケーという会社の名前から取っているんですよ。「バカばっかり会社」なんて呼ばれてたけど(笑)。デザイナーの荒牧太郎が乗っていた、フェラーリの「ベルネリッタ・ボクサー」の略だったかな。1990年にパパスと一緒にスタジオとカフェをやることにしたのですが、その運営をぼくの会社がやることになって、塚野事務所をビービーに変えたというわけです。今はぼくの会社の運営ではないんだけどね。その後ビービーケーケーがパパスになった。・・・つまんないでしょ? こんな話。
怖くてすごい!
デザイナー荒牧太郎伝説

いやいやいやいや! 面白すぎます。それが広尾のパパス社屋の近くにある、パパスカフェとビービースタジオというわけですか・・・。ようやくデザイナーの荒牧さんの話がでてきましたが、塚野さんとは長いんですよね?
塚野 荒牧さんの元奥さんは「フーチ」というあだ名のスタイリストだったんです。彼女と立木さんは1960年代前半にアドセンターという会社で一緒に働いていたから、その頃からの仲かな。当時荒牧さんはパリにいて、1964年にフーチといっしょにマドモアゼルノンノンを立ち上げるんですが、原宿にお店がオープンしたのに日本に帰ってこない(笑)。仕方がないから、ぼくとフーチがふたりで店番をやっていました。
1964年といえば東京オリンピックの年! マドモアゼルノンノンはもうすぐで創業60周年か・・・。ものすごいブランドですね。荒牧さんはどんな方でしたか?
塚野 う〜ん・・・。一種の天才ですかね。天才って、みんなちょっと狂った部分があるじゃないですか。彼はそれを持ち合わせている人間でした。普通ファッションデザイナーって、洋服といっしょに、自分自身の存在も社会に対して売り込むじゃないですか。彼はそういうことをしなかった人間なんですよね。・・・ぼくなんかの話よりも、太郎のことをもっと話そうよ(笑)。

承知しました(笑)。たしかに、同世代のデザイナーさんでいうと、高田賢三さん、コシノジュンコさん、稲葉賀恵さん、三宅一生さん、菊池武夫さんといった方々がおられますが、荒牧太郎さんの存在は、一般的にはそれほど知られていないですよね。実をいうと、ぼくは20年以上ファッションエディターをやっていますが、パパスは一切ファッション誌への露出もしないし、展示会にすら誘われたことがありません。ちょっと謎めいた存在でした。
塚野 そのスタンスがぼくは好きでしたね。
やっぱり、かなり神経質なタイプですか?
塚野 無頓着に見せることに対して、すごく神経質でしたね。気取っているところを絶対に見られたくない。そして絶対音感に比する、絶対色感のようなものを持っていたと思います。あとは貧乏くさいのだけは異常に嫌っていました。
貧乏くさいってのは、具体的にいうとどんなことですか?
塚野 たとえば靴下がナイロンのスケスケのやつだったりするような。ぼくもそう思いますけどね。

そのこだわりは身近な人にも発揮されるんですか?
塚野 最近は会社が大きくなって目が届かなくなっていましたが、昔はよく怒っていましたよ。
某情報筋からのタレコミによると、パパスのスタッフさんの間で〝見えない靴下〟が流行ったとき、荒牧太郎さんがそれを見つけて烈火の如く怒って、お前ら全員靴下脱げと(笑)。スタッフ全員で丸の内のショップに走って、靴下の棚が空っぽになったらしいですね。天才には伝説がつきものですが、荒牧太郎さんの逸話は各方面から耳にしております(笑)。原宿にあった頃のマドモアゼルノンノンでは、自分の服が似合わなそうなお客さんがくると、あんたに売る服はないと容赦なく追い返していたとも聞きました。
塚野 流行を疑いなく取り入れたり、振り回されたりしているようなのは、本当に嫌がっていましたね。まあ自分のスタイルをつくるには、それくらいのパワーがないと。三宅一生さんなんかもそうだったと思いますよ。
ぼくたちの仕事って、理論化できないセンスを題材にしているのが難しいところで、それを否定されると人格を否定されたような気分になっちゃうんですよね。それでときに恨みに思われたりもするし。
塚野 普通の人は、他人にダサいとか言えないよね。でも彼らはそれを平気で言い切れちゃう人たちなんだよ(笑)。ほとんど●●●●だよね。
紙一重の天才ってことですね(笑)。パパスがつくるものはリラックスしたカジュアルウエアで、値段はさておきテイストは極めてフレンドリーですが、その裏には極限の美意識があったんだなあ・・・。三宅一生さんや山本耀司さんらとは作風こそ全く違えど、こだわり具合は引けをとりませんね。今でこそゆったりめの服がトレンドになって、パパスが再注目されている現象がありますが、それこそピタピタの服が流行っているときだって、このフィット感を貫いてきたんですものね。

塚野 美意識なんていうとまた太郎に怒られるけど(笑)、自分だけのコードを持っていた。いい意味で非常に狭い枠のなかでデザインしていましたね。「ヘミングウェイが生きていたら着そうな服」っていう。ぼくはいつもこんな狭い枠でいいの?って思っていたけれど。でも、ひとつの世界観をつくっているからこそ、20年前のものでも普通に着られちゃうし、今のものと昔のものをミックスしてもおかしくない。
その狭さは、ある意味では天才の条件ですよね。でも、そういう美意識の塊と仕事ができた塚野さんもすごいですよ!
塚野 まあ、多少は認めてくれたんでしょうね。設立のときはぼくもたくさん資料を提供したし、ロゴも書かせてもらったし。あのロゴはサインペンでサッと描いて見せたら、そのまま採用されちゃったんだけどね。「ぼくのおじさん」のロゴも、ぼくが描いたらもっといい感じになるよ(笑)。
もっと早くお会いしたかったです(笑)。しかしパパスのテイストって面白いですよね。アメカジのようでアメカジでないというか。

塚野 太郎はパリにいたしね。ヘミングウェイがパリで暮らしたように、パパスにはヨーロッパの血がどこかに入っているんですよ。
しかし、丸の内店の内装はもうヘミングウェイの世界そのものですが、あれは塚野さんが関わられているんですか? もう世界的に見てもあんなお店は存在しませんよ。
塚野 いや、あれは完全に荒牧ワールドです。パリのカフェをイメージして、素材をぜんぶヨーロッパから輸入して。あれを許した会社も偉いですよ。だって野球選手と同じで、いち契約デザイナーなんですから(笑)。
えっ、そうなんですか?
塚野 そうですよ。当時はオーナーだって口を出せなかったんだから(笑)。本社の前にあるダビデ像も原寸大で、イタリアに行った時に買ってきたんですよ。
広尾のダビデ像の謎がようやく解けました。よっぽど怖かったんでしょうね(笑)。しかしよく塚野さんはそんな方と付き合えましたね。立木さんもいまだに怖いし(笑)。
塚野 まあ、それが才能ですよね(笑)。最初は友達で、毎晩キャンティで飯を食べていました。いっしょに仕事をするようになってからは、どうしたって関係性は変わってしまったけれど。
もう話してもいいかな。
パパスの極太ゴシックに
まつわる秘話

今や古本屋さんでは高値で取引されているPAPAS BOOKに関しても、荒牧さんが編集長的な存在だったんですか?
塚野 最初はぼくに任せきりだったんだけど、わかってくるにつれてどんどん口を出すようになったね。
PAPAS BOOKから広告まで、パパスまわりのデザインに共通する極太ゴシック文字は塚野さんのご趣味なんですか?
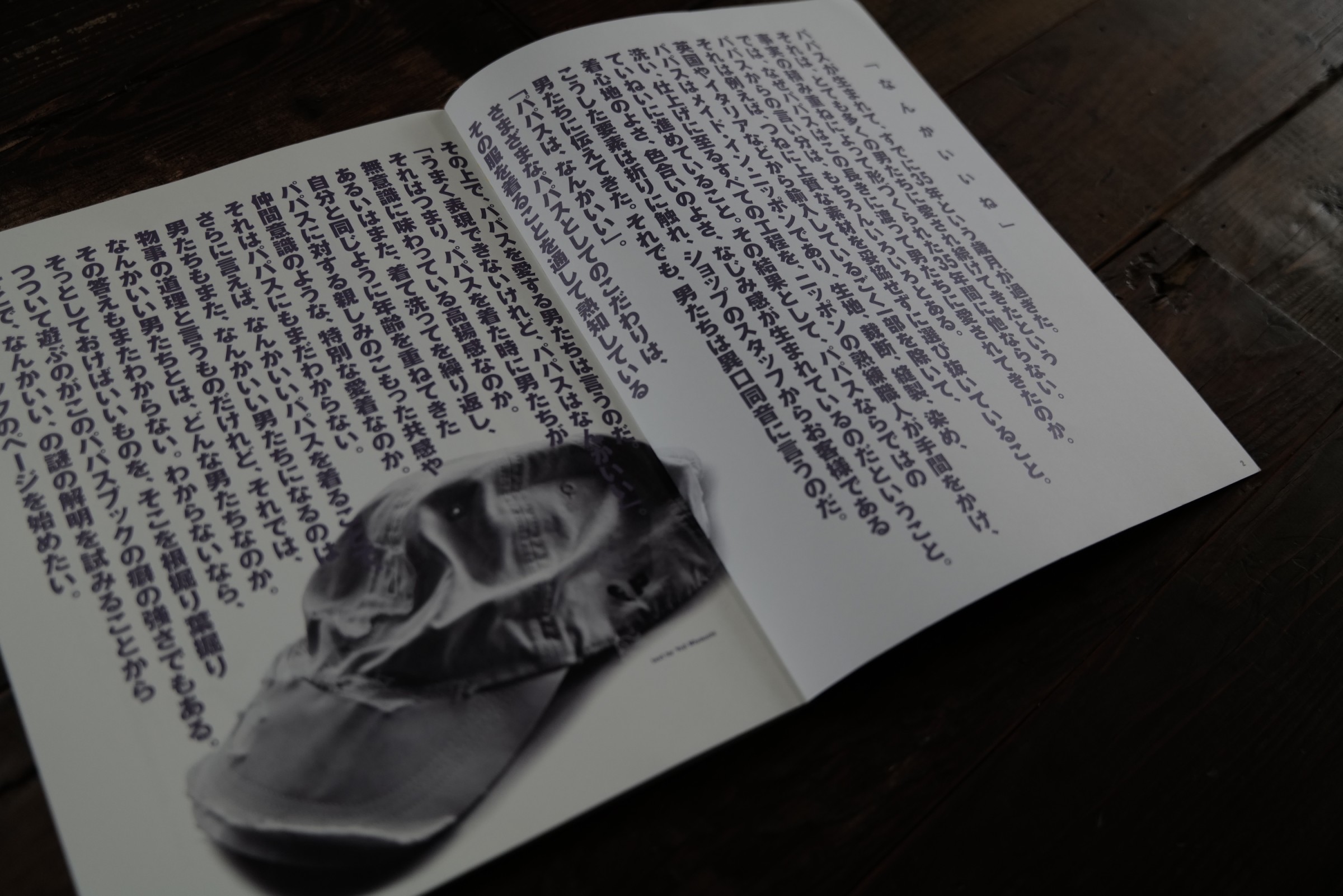
塚野 まあそうなんですけど、あれはデザインよりも予算が優先したんですよ。昔の写植文字って、文字数じゃなくてスペースで値段が決まるんです。なのでもともと小さい字をコピーで拡大してページを埋めるようなことをやっていたら、それがスタイルになっちゃった(笑)。まあ、そろそろちょっと変えないとね。
まさかそんな理由が・・・いや、今となってはあれがいいので変えないでください(笑)。
塚野 あの本はもともといろんな編集者やライターがつくっていたんだけど、いつも太郎とケンカしちゃうんだよ。それでいよいよやる人がいなくなって、ビービーでつくるようになったんです。で、あまり複雑な構成にするとややこしくなるから、なるべく単純な構成にして、ヘミングウェイを出して、太郎が好きな人に着てもらって、時計や葉巻なんかのテーマをやって・・・。そうやって太郎をなだめながらつくったんです。



JAZZからアメリカンカルチャーにハマった塚野さんが、いつしか和のライフスタイルに傾倒したのは、奥様の影響が強いという。どこか白州正子さんを彷彿させる、とても格好いい方だった。
次から次に新事実が発覚しますね。独裁型編集長のいる編集部にはよくある光景ですが、それが期せずして独特のスタイルをつくるから面白いですよね。しかしピエール・バルーが築地をふらふら歩いていたり、三國連太郎さんや谷啓さん、夏八木勲さんなど、本当に素晴らしいキャスティングですよね。お金がないとは思えない(笑)。
塚野 アメリカならヘミングウェイ、ヨーロッパならピカソ、日本なら三國連太郎だろう、ということでね。ぼくは三國さんとはプライベートでも付き合いがあったんだけど、彼は短パンに草履履きの浮浪者みたいな格好で渋谷をふらついていたかと思うと、別の日はバチッとスーツにタイドアップして銀座を闊歩していたりする。ぼくは今でも三國さんが、日本でいちばん洋服をうまく着こなせる人だと思いますね。

三國さんの逸話はよく伺いましたが、ぼくも本当にそう思います! しかし荒牧さんのことだから、三國さんとももめちゃったりして。
塚野 それが、そういう人とはうまくやるんだよね(一同爆笑)。
なるほど(笑)。しかしモノクロ写真ばかりで商品がほとんど載っていないPAPAS BOOKといい、空前絶後のショップといい、カフェといい、荒牧さんのスケールはとてつもないですね。
塚野 昔から文化なんてものはさ、ときの権力者が道楽でつくったものが、後になってそう呼ばれるようになったんですよ。
確かに、ルネサンス運動を例に出すまでもなく、文化には天才と権力者、そしてパトロンの存在がつきものですからね。荒牧さんがダビデ像を買ってきた理由がわかりました(笑)。しかし塚野さんがそんな困った天才・荒牧太郎さんと半世紀にわたってお付き合いができたのは、やっぱり抗いきれない人間的な魅力があったんでしょうね。
塚野 まあお互い認め合っていたのかな。
やっぱり特別な人物だった?
塚野 まあ、そうですね。毎日会っていたしね・・・。昔は会社の人も太郎が怖すぎて、直接言えないことは、ぜんぶぼくを通していたんですよ。だからあだ名は避雷針(笑)。いつも雷がぼくのところに落ちるの。ここだけの話、昔はその手当てをちょっともらっていたんですよ。
荒牧さん手当て・・・最後になってまたすごい逸話をぶち込んできた(笑)! もう話は尽きませんね。パパスって奥が深いブランドだなあ。ぜひ今度は六本木の話を聞かせてください!



1936年(昭和11年)新潟県生まれ。広告デザインやブランディングなどを中心に活動する、株式会社ビービーの代表。パパスのビジュアル以外にも、2022年にはアイウエアブランドZOFFの雑誌広告で、第59回JAA広告賞の雑誌広告部門でメダルを受賞。86歳にしてそのセンスは円熟の極みに達している。